 |
 |
 |
 |
| �i�P�j�n��T�v |
|
| |
���Ώۍ�
�@���{
���Ώۓs���{��
�@���Ɍ�
���Ώێs����
�@���s�i�Ώےn��F���ՊC�n��j
���n��T�v
�@���s�l���@ �S�U���l�A�]�ƎҐ��@�Q�O���l
�@�i�Ώےn��̂݁@�l��1.5���l�A�]�ƎҐ�2.3���l�j
�@�ʐρ@ �T�O�����Q
�@�i�Ώےn��̂݁@�P�O�����Q�j
����ʈړ��T�v
�@��\��ʎ�i�@��4��_�s�s���o�s�����i����12�N�j
�@���s�f�[�^�i�Ώےn��̂݃f�[�^�j |
| |
������
�o�X
�S�� |
19.4��
3.5��
15.4��
|
|
�i40.5%�j
�i 4.1%�j
�i15.3%�j |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| �i�Q�j��g |
|
| |
����萼�{�ՊC���ɂ�������ɂ₳������ʊ�ՁE�V�X�e���̍\�z���f������
���T�v
|
| |
|
�@����43���ƍ�_�����p�ݐ��ɋ��܂ꂽ���ՊC�n��ɂ�����r�C�K�X�ɂ���C�ւ̕��S��ጸ���邽�߁A�o�X�̗��p���i���⎩�]�ԓ��̐����A���s��Ԃ̊m�ۂ�}�邱�Ƃɂ�鎩���ԗ��p�̗}����}��ق��A�ᑛ���E�������ܑ��̎��{�A�ؐ��h��̓��H�{�݂�����B
|
| |
|
| |
���n��v��ł̈ʒu�Â� |
| |
|
| |
|
|
�v����
|
�ȃG�l���M�[�r�W�����i���Ɍ��j
|
�܂��Â���̍\�z
|
| �v��Ȃǖ��� |
�O���[���G�l���M�[���i�v���O���� |
���21���I�̐X�\�z |
| ����N�� |
�Q�O�O�Q�N7�� |
�Q�O�O�Q�N�R��
|
| �ڕW�N�� |
�Q�O�P�O�N�x |
--------- |
���֘A�ڕW�l
|
�팸���ʁi�������Z�@�������j
�R�T�S�D�W
|
--------- |
|
| |
|
| |
��EST���f�����ƂɌW��ڕW�l |
| |
|
�T�Z�r�o��
�@�T�Z�r�o�ʁF�P�T�D�P�����|CO�Q�^�N�ԁi�P�D�T���l�~�P�O�D�P���\CO�Q�^�N�ԁj
�@�T�Z�����Ԕr�o�ʁF�Q�D�V�����|CO�Q�^�N�ԁi�P�D�T���l�~�P�D�W���\CO�Q�^�N�ԁj
�ڕW�l
�@�ڕW�ጸ�r�o�ʁF328���|CO�Q�^�N
�@�ڕW�N���F�����Q�V�N�x |
| |
|
| |
����g��@ |
| |
|
|
|
|
��R��ԓ���
|
���H����
|
��ʊǗ��̍��x��
|
������ʉ��P
|
���s�ҋ�Ԃ̏[��
|
�s���ϗe
|
���̑�
|
|
-----
|
��
|
-----
|
-----
|
��
|
��
|
-----
|
| |
�i�s�j����ː��̐��� |
|
|
��������������E���[�h�̐���
���ɂ₳�������]�ԗ��p��Ԃ̐���
�����̃Z�~�t���b�g��
�Ԕ��ނ𗘗p�����ؐ��h���̐ݒu |
�ՊC�쐼���̏]�ƎҁE���K�҂ւ̃��r���e�B�E�}�l�W�����g |
�����A��Ԃ̗}��
�G�R�h���C�u |
|
|
| |
���i�s�j����ː��̐��� |
| |
|
�@���ՊC�n��̎����Ԍ�ʗ��̉~��������ړI�ɁA�s�s�v�擹�H����ː��̐����i���H�g�����j�B��ʊ��q�[�g�A�C�����h���ۂ̕��ׂ�ጸ�����邽�߁A�ԓ��ɔr�����ܑ��A�����Ɍ��G�}���{�����������ܑ���
|
|
| |
����������������E���[�h�̐��� |
| |
|
�@��_���w�y�яo���~�w�Ɠ��̐X�����Βn�����ԁA�S��6km�̃o���A�t���[�̎��_�ɗ��������S�E���S�E���K�Ȏ��]�ԓ��̐���
|
|
| |
�����ɂ₳�������]�ԗ��p��Ԃ̐��� |
| |
|
�@�����̗ǍD�Ȏ��]�ԁE���s�ҋ�Ԃ����p���A���̐X�����Βn�̋ߗw�ł��镐�ɐ�w�═�ɐ�c�n�O�w����̎��]�ԓ��l�b�g���[�N�̌����E����
|
|
| |
�������̃Z�~�t���b�g�� |
| |
|
�@�����b�q�������i�o���~���y�їՍ`���j�ɂ����āA�����̎��]�ԕ��s�ԓ��̒i�����������A�N�������S���ė��p�ł��郆�j�o�[�T���f�U�C���̕�������
|
|
| |
���Ԕ��ނ𗘗p�����ؐ��h���̐ݒu |
| |
|
�@�����b�q�������i�o���~���y�їՍ`���j�ɂ����āA�����Y�Ԕ��ނ�h���Ɋ��p
|
|
| |
���ՊC�쐼���̏]�ƎҁE���K�҂ւ̃��r���e�B�E�}�l�W�����g |
| |
|
�@���ՊC�n��̏]�Ǝ҂���̐X�����Βn���ւ̗��K�҂�ΏۂɁA�}�C�J�[�ł͂Ȃ��A�k���A���]�ԁA�H���o�X���ɂ��ʋ◈�K�������I�ɍs���Ă��炤���߂̓�������
|
|
| |
�������A��Ԃ̗}�� |
| |
|
�@���Ə��̉c�Ǝԗ��̎���ւ̎����A��A�c�Ǝԗ��ł̒ʋ̗}���̓�������
|
|
| |
���G�R�h���C�u |
| |
|
�@��ƂɁA�h���C�o�[�ɃG�R�h���C�u�̏�����w������悤����������
|
|
| |
���o�X��ʏ[���Ƃ��Ẵ��r���e�B�E�}�l�W�����g |
| |
|
���Љ�����̖ړI
�@���21���I�̐X�Â���𐄐i���A���ɂ₳�����܂��Â����i�߂��ŁA���ՊC�n��̌�ʗ��������߁A���_�n��ւ̃A�N�Z�X������͂���o�X��ʂ̏[�����ۑ�ƂȂ��Ă����B
�@���̂��߁A����17�N�x�Ƀ��r���e�B�E�}�l�W�����g�Ȃǂ̎Љ�������s���A�o�X�[���̉\����c�����A����̃o�X�[������̕����������������B |
| |
|
|
|
�}�|�P�@���21���I�̐X�\�z�Ώۋ��Ƃ��̋����̃o�X�H����
|
| |
| |
| �i�R�j���� |
|
| |
|
�E�o�X�T�[�r�X�����サ���������Ə��Q�Ђ̏]�ƈ�338���̋��͂邱�Ƃ��ł����B
�E����338�l�̂���12�l�i3.6%�j���ʋΎ�i��ύX�����B
�E�A���P�[�g���ʂɂ��Ɓu�ʋΎ�i��ύX�\�A�ꍇ�ɂ���Ă͉\�v�Ɠ������l����110�l�������Ƃ������荡��̃o�X�[������ւ̏d�v�ȃf�[�^�邱�Ƃ��ł����B
|
| |
|
| |
���T�v |
| |
|
�@���ՊC�����̐V�K��Ƃ̊J�Ƃɔ����A�n������^�s����H���o�X�̏[�����}���邱�Ƃ����������ɁA�o�X���[�g�����ɗ��n���鎖�Ə��Q�Ђ̏]�ƈ��i��700�l�j�ɁA�����Ԃł͂Ȃ��A�k���A���]�ԁA�H���o�X�ɂ��ʋ𑣂����������i���r���e�B�E�}�l�W�����g�i�ȉ��l�E�l�j�j���s�����B�l�E�l���{���̎Q���ҁi�A���P�[�g�Ґ��j�͖�300�l�ł������B |
| |
|
|
|
| |
����g��@�i���r���e�B�E�}�l�W�����g�j |
| |
|
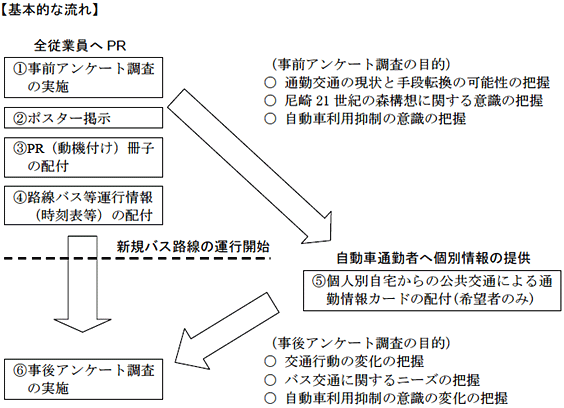 |
| |
| |
|
�z�t�����̗� |
| |
�BPR�i���@�t���j���q |
|
|
| |
| |
|
|
�D�l�ʎ����̌�����ʒʋΏ��J�[�h |
|
|
| |
| |
| �i�R�j���� |
|
| |
|
�@���O�A���P�[�g�ł́A�ʋΎ�i�ɂ��Č�����ʂւ̓]���\�������Ƃ���A�����ԗ��p�҂̖�5�����ł���A�ꍇ�ɂ���Ă͂ł���Ɠ����Ă���A�o�X�T�[�r�X�̏[���ɂ���ẮA�]��������ݓI�ȉ\�����m�F�ł����B |
| |
|
�\�|�P�@�ʋΎ�i�̕ύX�i���O�A���P�[�g���ʂ��j
|
|
|
| |
|
�\�|�Q�@�ʋΎ�i�̕ύX�i����A���P�[�g���ʂ��j
|
|
|
| |
| |
�����ʌ��̎�@�̓�����g��@�i���r���e�B�E�}�l�W�����g�j |
| |
|
�@�l�E�l���~���Ɏ��{���邽�߁A�w���o���ҁA�n��W�ҁA��ƊW�ҁA�o�X���ƎҁA�s�����Q���������k���ݒu�����B���k��ł́A�n���ʂ̏Ƃ������L�����_����A�Љ�����̎�@�Ɏ���܂ł̈ӌ��������s���A���ՊC�n��̃o�X��ʏ[���Ɍ����Ď��g�B |
| |
| |
| �i�R�j���� |
|
| |
�����{�̌��� |
| |
|
�����P�W�N�x�̍팸���ʁF33�� |
| |
| |
�����ʌ��̎�@�̓��� |
| |
|
�����ԓ]���䐔�̔c��
�E���v���@�F�����Ԃ���̓]���䐔����R������G�l���M�[���M�ʂ����߁ACO�Q�r�o�W�����|���邱�Ƃɂ��ACO�Q�팸�ʂ��Z�o�B
�������ʃK�X�r�o�팸�̎��Z���@
�ECO�Q�r�o�W���F�n�����g����̐��i�Ɋւ���@���{�s�ߑ�O��ʕ\��� |
| |
| |
| �i�S�j�]�� |
|
| |
|
�@�Ώےn��͎Y�ƍ\���]���̂��ߋn�ɂȂ����ՊC�n��̍Đ��v�悪���肳��Ă���i���21���I�̐X�\�z�j�B�ŋ߂̍D����w�i�ɁA���̒n��ɍH�ꗧ�n���i��ł���A���̏]�ƈ��̒ʋΌ�ʎ�i�̊m�ۂ��ۑ�Ƃ��Ă���B
�@���̉ۑ�̉����Ɍ����āA�n��W�ҁA�o�X���ƎҁA�s���������������k���ݒu���A�n��̌�����ʑ����l���悤�Ƃ����_���]�������B
�@�����̏]�ƈ��ɑ���MM�Ƃ��āA�V�K���n�ɂ��킹�Ď��{���A��Ƃ̃j�[�Y�ɑΉ��������h�T�C�Y�̘H���o�X�����\�쐬�Ȃǂ����܂ꂽ�B�܂��p���I�ɔz�z���Ă���������悤���Ə��ɓ����������_���V�����B
�@�ʋ����ł͂Ȃ����̎��Ɏg�p�����v�[���̊J�݂ȂǁA�V�K���v�����܂��Ă���n��ɁA�����̌�ʎ��Ǝғ��̋��͂̉��A���ɔz��������ʃV�X�e�����\�z�ł��邩����Ɋ��҂������B
|
| |
|
|
| |
| �i�T�j�A����A�W���� |
|
| |
|
���Ɍ����y���������y����21���I�̐X��
���d�b�ԍ��@078-362-9243
��FAX�ԍ��@078-362-9264
�����[���A�h���X�@kendo_21c@pref.hyogo.jp
|
